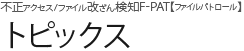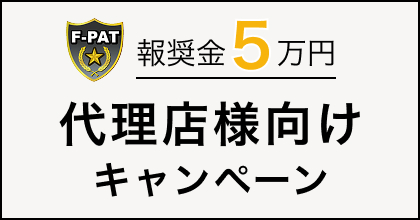2025年7月10日(木)
「見せ方」から守るWEBセキュリティ──Sorryページのあり方
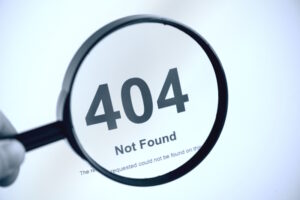 あなたがWEBサイトの管理者であるなら、パスワードやウイルス対策ソフトの話と並行して見直してほしいのが、エラーページ(Sorryページ)やメンテナンス画面です。
あなたがWEBサイトの管理者であるなら、パスワードやウイルス対策ソフトの話と並行して見直してほしいのが、エラーページ(Sorryページ)やメンテナンス画面です。
意外かもしれませんが、これらは攻撃の起点になりやすく、WEB改ざんやDDoS攻撃と密接な関係があります。一方、「Sorryページ」とよく似た名称で「Sorryサーバー」というセキュリティに関するサーバーの構成要素の1つがあります。この両者の違いについても触れます。
今回は、セキュリティ初級者にもわかるよう、次の4つを順を追って解説します。
- なぜSorryページが危険なのか
- 改ざんとDDoS攻撃の実例と流れ
- Sorryサーバーとは何か?なぜ必要か?
- 企業が今から実践できるセキュリティ対策
1. Sorryページが“情報漏れ”の入り口になる
Sorryページとは、エラーやメンテナンス時に表示されるページの総称です。
代表例:
- 404 Not Found(ページが存在しない)
- 403 Forbidden(アクセスが許可されていない)
- 500 Internal Server Error(サーバー側の異常)
- 503 Service Unavailable(一時的に利用不可、メンテナンス中)
これらは本来、「ユーザーに状況を伝えるための画面」ですが、作りが甘いと攻撃者への「情報提供ページ」になってしまいます。
実際にありがちな例:
ページが存在しない時に表示される「NotFound」ページ
404 Not Found
/home/www/html/wp-content/themes/corp/page.php が見つかりません。
Apache/2.4.53 Server at www.example.com
この情報だけで、攻撃者はこう推測できます:
- WordPressを使っている
- テーマの構成が把握できる
- サーバーのバージョンに既知の脆弱性があるか確認できる
つまり、Sorryページから攻撃の足がかりが生まれてしまうのです。
2. 改ざんやDDoS攻撃とどうつながるのか?
WEB改ざんの入口になるパターン
- SorryページからCMSや構成情報を収集
- 古いプラグインやテーマの脆弱性を調査
- 管理画面やFTPへの不正アクセスを試行
- 改ざんされたページに悪質なコードが挿入される
- ユーザーを偽サイトへ誘導 or SEO汚染が発生
とくにWordPress系サイトでは、テンプレートファイル(404.phpなど)自体が改ざん対象になり、ユーザーに気づかれずに不正広告やフィッシングが仕込まれるケースもあります。
DDoS攻撃による「見せ方崩壊」
DDoS(分散型サービス拒否)攻撃は、大量アクセスを一斉に浴びせ、サーバーをダウンさせる攻撃です。
このとき、
- SorryページがCMS経由で生成されている
- 動的に重い処理をしている
- ログイン画面や余計な情報が表示される
といった状態だと、負荷が増幅し、攻撃を助けてしまうことも。
3. SorryページとSorryサーバーの違いとは?
多くのWEBサイトには、ページが見つからない時やメンテナンス中に表示される「Sorryページ(お詫びページ)」が存在します。これはユーザーに状況を伝えるための画面レベルの仕組みであり、主にHTMLやテンプレートで構成されます。
一方で「Sorryサーバー」は、それとはまったく別物です。
Sorryサーバーとは、本番のWEBサーバーとは別に用意された、障害時専用の静的な代替サーバーのこと。WEBサーバーに障害が発生したり、DDoS攻撃で負荷が限界を超えたとき、自動的にこのSorryサーバーに切り替えることで被害の拡大を防ぎます。
▼ 違いをまとめると:
- Sorryページ:
通常のWEBサーバー内にあるテンプレートやHTMLファイル。CMSの一部として動作。
アクセスエラーやメンテ時に表示されるページ単位の処理。 - Sorryサーバー:
本番とは別に構築された静的WEBサーバー。障害時にルーティングを切り替えて使用。
サーバー全体が落ちても“最低限の案内”をユーザーに返す独立構成。
構成イメージ
- 通常時:CMSが稼働するWEBサーバーでコンテンツ配信
- 異常時:ロードバランサーやCDNがSorryサーバーへ自動切り替え
→ 軽量な静的HTMLのみを返し、余計な処理は一切しない
Sorryサーバー導入のメリット
- 静的なためDDoSに非常に強い
- 動的処理がなくサーバー負荷を最小化
- 攻撃者に技術的ヒントを一切与えない構成にできる
- メンテ中でも信頼性と誠実さを保った対応が可能
Sorryページはユーザー向けの「見せ方」であり、Sorryサーバーはシステムレベルの「守り方」です。両者を併用することで、WEBサイトのセキュリティと信頼性は大きく高まると言えます。
4. 企業が今すぐできるセキュリティ対策
Sorryページの改善ポイント
- ファイル名・構成情報は表示しない
- ステータスコード(404/503など)は正確に返す
- CMSで生成せず、できるだけ静的HTMLにする
- 問い合わせ先・トップページへのリンクだけに絞る
改ざん・DDoSへの基本対策
- WordPressなどのCMSは常に最新バージョンへ更新
- 管理画面にIP制限(社内からのみアクセス可能に)
- WAFの導入(クラウド型・アプライアンス型どちらでも可)
- ファイル改ざん検知ツール(例:Wazuh、AIDE、F-PAT)を導入
- バックアップと復旧手順を明文化・定期テスト
Sorryサーバーの導入を検討
- 静的HTMLでデザインした軽量なSorryページを別サーバーに設置
- 異常検知時は自動でSorryサーバーにルーティング切り替え
- たとえばCDN(Cloudflare等)+静的ホスティング(S3、Netlifyなど)で構築可
見せない設計と「もしも」への備えが信頼を守る
WEBセキュリティの基本は、「そもそも入られないようにすること」です。
ファイアウォール、脆弱性対策、強固な認証など、技術的な防御は当然必要です。
ただ、それだけでは十分とは言えません。

攻撃者に余計なヒントを与えない設計──たとえばSorryページの簡素化や構成情報の秘匿。
万一入られた場合に備えた対応──改ざん検知、ログ管理、Sorryサーバーの運用。
これらを組み合わせておくことが、被害の拡大を防ぎ、企業としての信頼を守る鍵になります。
まずは、自社サイトの「見え方」「エラーの扱い」「ダウン時の対応」に目を向けるところから。
それが、攻撃されても慌てずに済む、堅実なセキュリティ体制への第一歩です。