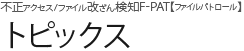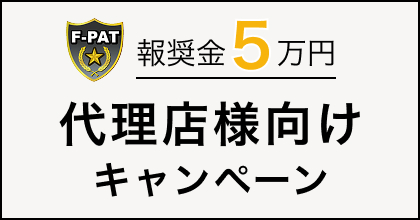2025年9月5日(金)
AI活用で進化するWEBサイトセキュリティ ― 現状と未来
 WEBサイトは企業の信頼を支える窓口であり、同時に攻撃者にとって最も狙いやすい標的でもある。フィッシング、不正ログイン、ボット攻撃、ゼロデイ脆弱性など、脅威は巧妙化・多様化を続けている。従来型のシグネチャベース防御だけでは限界があり、近年はAIを活用したWEBセキュリティが急速に普及している。
WEBサイトは企業の信頼を支える窓口であり、同時に攻撃者にとって最も狙いやすい標的でもある。フィッシング、不正ログイン、ボット攻撃、ゼロデイ脆弱性など、脅威は巧妙化・多様化を続けている。従来型のシグネチャベース防御だけでは限界があり、近年はAIを活用したWEBセキュリティが急速に普及している。
本稿では、まず日本国内ですでに導入されているAIセキュリティの事例を紹介し、そのうえで今後の可能性、攻撃者によるAI活用のリスク、さらに課題と人間の役割について考える。
1. すでに実用化されているAIセキュリティ
(1)AIによる異常検知
AIを活用したログ解析や異常検知は、すでに商用サービスとして広く使われている。従来の仕組みは「既知の攻撃パターン」をシグネチャとして登録しないと検知できなかったが、AIはアクセスや通信のパターンを学習し、「いつもと違う動き」をリアルタイムで検知できる。
たとえば、深夜に特定IPから急激にログイン試行が増えた場合、AIは単なる回数の異常だけでなく、行動パターン全体の変化を読み取り「不正の可能性あり」と判断できる。これは人間の直感に近い仕組みだ。
日本では、NTTセキュリティの「WideAngle」 がこの領域で実績を持つ。大規模ネットワークのトラフィックをAIが常時解析し、未知の攻撃も検出できる体制を提供している。また、日立製作所の「JP1/Integrated Management」 では、システム運用ログにAI分析を組み込み、障害や攻撃につながる異常の兆候をいち早く検出している。
(2)AIによるボット対策
悪質なボットはスクレイピングやチケットの自動購入、クレデンシャルスタッフィングなどに悪用されている。CAPTCHAはすでに突破されやすくなっており、AIによる行動分析型の防御が主流になりつつある。
AIは、マウスの軌跡、入力速度、スクロールの癖といった微細な特徴を学習して「人間らしさ」をスコア化し、ボットとの判別精度を高める。大手ECや金融機関では、これにより不正アクセスの削減に成功している。
国内でも、Akamaiの「Bot Manager」 がEC業界や金融業界で広く導入され、AIを活用して不正な自動化アクセスを遮断している。また、ソフトバンクが提供するクラウド型WAFサービス もAIを搭載し、ボットによるアカウント攻撃をリアルタイムで防御する仕組みを実用化している。
(3)インシデント対応の自動化
AIは「検知」だけでなく「対応」のスピード向上にも貢献している。SOAR(Security Orchestration, Automation and Response)ツールでは、AIがログを分析し、攻撃元IPの遮断や影響範囲の洗い出しを自動で実行する。従来なら数時間かかる作業が数分で完了するのは大きな価値だ。
日本市場では、トレンドマイクロの「XDR」ソリューション が代表的だ。AIが複数のセキュリティログを相関分析し、アラートを絞り込み、対応を自動化している。また、富士通の「Managed Security Service」 もAIをSOC運用に取り入れ、運用者の負担を軽減しつつ検知精度を高めている。
2. 今後に期待されるAIとセキュリティの進化
現在のAIセキュリティは「検知・分析・自動化」が中心だが、将来的にはさらに高度な応用が進むと期待されている。
自動ペネトレーションテスト
攻撃者が使う手法をAIが模倣し、自動で脆弱性を突く「模擬攻撃」を行う仕組み。これにより防御側は、未知の弱点を発見して修正するサイクルを短期間で回せる可能性がある。
自律型セキュリティ
AIが検知から対処まで完全に自律的に実行する仕組み。ネットワークを監視し、異常を検知したら人間の承認を待たずに自動で封じ込める。企業の運用コストを大幅に下げる一方で、誤検知リスクへの配慮も必要となる。
中小企業への普及
クラウド型のAIセキュリティサービスは低コストで提供可能なため、専門人材が不足する中小企業にも普及が進むと予想される。大企業だけの武器ではなくなる点が重要だ。
3. 攻撃者もAIを使う時代へ
ただし、AIを利用するのは守る側だけではない。攻撃者もAIを積極的に取り入れ始めている。
生成AIによるフィッシング
自然な日本語メールや偽サイトを大量自動生成し、従来より巧妙な詐欺が可能になる。
AIによるCAPTCHA突破
機械学習で画像認識を訓練し、人間しか解けないはずのテストを突破する。
敵対的AI攻撃
防御用AIにノイズを与えて誤認識を誘発する「対AI攻撃」も研究段階から実用段階へ移行しつつある。
今後は「AI対AIの攻防」が主戦場になると考えられる。防御側が技術更新を怠れば、逆にAIを使った攻撃に追いつけなくなるリスクがある。
4. AIセキュリティの課題と人間の役割
 AIはセキュリティに大きな力を発揮しているが、同時にいくつかの課題が存在する。
AIはセキュリティに大きな力を発揮しているが、同時にいくつかの課題が存在する。
1. 誤検知・見逃しのリスク
学習データの偏りや不足によって、攻撃を正常と判断したり、通常のアクセスを攻撃と誤判定する可能性がある。これにより業務に支障をきたすケースも報告されている。
2. ブラックボックス化の問題
AIが「なぜその判断に至ったのか」を人間が説明できない場合、セキュリティ担当者は対策を取りづらい。監査や法的説明責任を求められる場面では大きな課題となる。
3. AI依存による判断力の低下
「AIが見ているから安心」という思い込みは危険だ。AIが見逃した攻撃や新しい攻撃手法への初期対応は、人間の直感や経験に依存する部分が大きい。
こうした課題を踏まえると、AIセキュリティは「万能の防御システム」ではなく、人間とAIの協力関係で初めて力を発揮する仕組みだと言える。AIは膨大なデータを高速に分析する役割を担い、人間はその結果を解釈し、経営判断やリスク管理につなげる。
結局のところ、AIは「人間の判断を支える強力な補助輪」であり、AIと人間が補完し合う体制こそが本当のセキュリティ強化につながる。